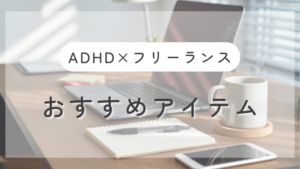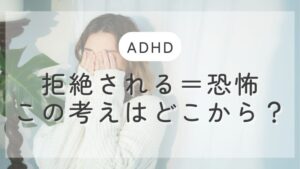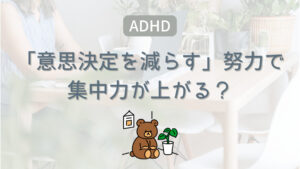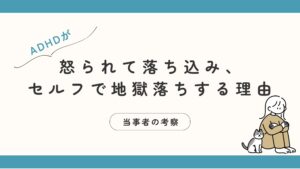「ADHDってINFPやINTPが多いらしい」
SNSやネット記事で、そんな声を見かけたことはありませんか?
MBTIの一部のでは、ADHDっぽい行動特性と重なる部分があります。そのためか、ADHDを名乗るSNSアカウントでも、「私はMBTIが◯◯だからADHDだ」のような発言がしばしば。
しかし、「ADHDに多いMBTIタイプ」が医学的に証明されたわけではありません。実際には、どのタイプにもADHDの人は存在します。
大切なのは、MBTIをADHD診断の代わりにすることではなく、自分の特性を理解し、環境や習慣を整えるための補助ツールとして使うことです。
今回では、「ADHDに多いMBTI」のような情報がバズりやすい背景や、ADHD×MBTIを自己理解や環境改善に活かす方法を詳しく解説します。
ADHDとMBTIの根本的な違い

| 比較項目 | ADHD | MBTI |
|---|---|---|
| そもそも何? | ・神経発達症のひとつ (病院で診断) | ・性格傾向を測る心理モデル (ネットで無料診断) |
| 診断の根拠は? | ・脳の機能 ・神経伝達物質の働き | ・認知の好み ・情報処理の癖 |
| 治療 | ・できる | ・できない |
| 症状や特性の変化 | ・一生続く傾向 (症状の出方は変化) | ・経験や環境で変化することも |
 めぐり
めぐりADHDとMBTIの一部の特性が似ていても、同じものではありません。
ADHDは医学的な診断や治療が可能。対してMBTIはあくまで「性格傾向」で、自己理解のサポートツールや相性診断として使われています。
ADHDとMBTIが混同されやすい理由


SNSなどでは、「このMBTIはADHD」のような決めつけを見かけることも。このようにゴチャゴチャに語られる理由として、次の3つが考えられます。
- 行動や印象の一部が似て見えるから
- ADHDとMBTIの“ラベル感”が似ているから
- バズらせるために混ぜ書き・誇張するケースがあるから
1.行動や印象の一部が似て見えるから
ADHDの特性でよくある…
- 衝動的
- アイデアが豊富
- 飽きやすい
- 集中力の波が大きい
などは、MBTIタイプの中でも外向型(E)・直感型(N)・柔軟型(P)といった組み合わせの行動傾向と重なる部分があります。
その結果、SNS上では「ENFPっぽい=ADHDっぽい」のようにADHDとMBTIを結びつける人が多々います。
2.ADHDとMBTIの“ラベル感”が似ているから
ADHDもMBTIも、4文字の短い略称で表現されていて、「どちらもラベルの一種」である点も共通しています。
私たち人間は、物事をわかりやすく把握するためにラベリングすることを好みます。



「私ってA型だから…」みたいなのもラベルのひとつ。
特にADHDや、MBTIの種類のように、短くてキャッチーなラベルは印象に残りやすいと思います。
そのため、ADHDとMBTIはラベルとしての性質が似ていることから、「自分を表すキャッチーなラベル」として似たような使い方がされやすいのではないでしょうか。
3.バズらせるために混ぜ書き・誇張するケースがあるから
ネットでは、ADHDとMBTIを組み合わせたインパクトあるコンテンツがよく見られます。



「ADHDの人に多いMBTIタイプTOP3」
「このMBTIはADHDと相性サイアク!」
などなど…
診断のような自分に当てはまる情報や、わかりやすいラベルに人は惹かれます。診断要素に加えて、短く印象的なフレーズが加わると、正確性よりも共感や面白さが優先され、拡散されやすくなるでしょう。
このような発信は話題性は高いものの、科学的な裏付けがほとんどない場合でも、「同じもの」または「強く関連している」という誤ったイメージを広めてしまいます。
ADHDとMBTIを正しい関係で理解し直すポイント


ADHDとMBTIが混同されやすい理由がだいたい見えてきたと思います。
ここからは、ADHDとMBTIの違いを踏まえつつ、「正しい関係」で理解してうまく活用するためのポイントをお話しします。
1.ADHDの有無とMBTIタイプに絶対的な関連はない
「ADHDの人はこのタイプが多いらしい!」なんて話もありますが、科学的な根拠はありません。



これ、すっごく大事な点なので何度でもお伝えします。
ADHDと似たような傾向のタイプはあっても、あくまで傾向・憶測レベル。
医学的な診断であるADHDと、心理傾向のMBTIタイプを直接結びつけることはできない!とハッキリ頭に入れておきましょう。
2.MBTIはADHDの人が自己理解するための参考になる
じゃあ、ADHDがMBTIについて考えることに意味がないのか?というと、そうでもありません。
MBTIは自分の認知や行動のクセを整理するきっかけになります。
ADHDの人にとっても、MBTIは「自分はこういう場面で力を発揮しやすい」「ここでつまずきやすい」といったパターンを見つける手がかりになるんです。
ADHD×MBTIで考える自己理解のヒント


MBTIの視点を取り入れることで、ADHDの人に合った環境や働き方のヒントを見つけやすくなります。
ここからは、MBTIの4つの指標(E/I・S/N・T/F・J/P)を切り口に、ADHDの特性を踏まえた環境調整のポイントなどを考察します。
E/I(外向・内向)で見る刺激とのつき合い方
E/I(外向・内向)は、MBTIで最初に出てくる指標で、「エネルギーをどこから得るか」を示しています。
- E(Extraversion/外向)
- 人や環境からの刺激によってエネルギーを得るタイプ
- I(Introversion/内向)
- 一人の時間や内面的な活動からエネルギーを得るタイプ
ADHDの人の場合、この「刺激の取り方」によって、集中力の出やすさや疲れやすさのパターンが変わります。
E(外向型)
刺激が多いほど活性化しやすいタイプです。新しい人との出会いや多様なタスクはモチベーションにつながりますが、その反面、過刺激で疲弊しやすい面も。
対策のポイントは、予定を詰め込みすぎないこと。
あえて「空白時間」をカレンダーに入れておくと、脳のクールダウンになり、集中力を保ちやすくなります。
I(内向型)
静かな環境で集中力を発揮しやすいタイプです。深く考える作業や一人での作業が得意ですが、孤立感を抱きやすいのが弱点。
対策のポイントは、意識的に人と関わる場をスケジュールに組み込むこと。
週1回の打ち合わせや勉強会など、人との軽い接点を確保することで、モチベーションや視野の広さを保ちやすくなります。
S/N(感覚・直感)で見る情報の扱い方
S/N(感覚・直感)は、MBTIで「情報をどのように受け取り、処理するか」を示す指標です。
- S(Sensing/感覚)
- 五感や事実ベースの具体的な情報を重視するタイプ
- N(iNtuition/直感)
- 全体像や未来の可能性といった抽象的な情報を重視するタイプ
ADHDの人にとって、タスクの進め方や計画の立て方の違いに直結します。
S(感覚型)
感覚型の人は、具体的で手順が明確な情報に安心感を覚えます。曖昧な指示や抽象的な話は混乱のもとになりやすく、動き出しが遅れることも。
対策のポイントは、やるべきことを細かく分解し、1ステップずつ進められる形にすること。チェックリストや進行表を活用すると安定して進められます。
N(直感型)
直感型の人は、大きなアイデアや全体像から発想するのが得意です。しかし、抽象的なままにしておくと、タスクが形にならず動けなくなることもあります。
対策のポイントは、ひらめいたらすぐに具体的なタスクへ落とし込むこと。思いついた瞬間にメモアプリや付箋に書き出し、最初の一歩を決めてしまうと行動につながりやすくなります。
T/F(思考・感情)で見る判断の傾向
T/F(思考・感情)は、MBTIで「物事を判断するときに何を優先するか」を示す指標です。
- T(Thinking/思考)
- 論理や客観的な基準を重視するタイプ
- F(Feeling/感情)
- 人間関係や感情的な影響を重視するタイプ
ADHDの人は、この判断スタイルによってストレスの感じ方や意思決定の詰まりやすいポイントが変わります。
T(思考型)
思考型の人は、論理的に物事を整理するのが得意です。ただし、人間関係や感情が絡む場面では「どう扱えばいいか分からない」と戸惑い、動きが止まることがあります。
対策のポイントは、感情が絡むシーンでも一度論点を紙に書き出して整理すること。
整理して論理の土台を作れば、感情の揺れに振り回されにくくなります。
F(感情型)
感情型は、人の気持ちや場の空気に敏感です。そのため、相手の感情を気にするあまり作業が中断されたり、自分の気持ちに引きずられやすい面があります。
対策のポイントは、感情を受け止める時間と作業時間を意識的に分けること。「まず気持ちを吐き出す→区切って作業に戻る」という流れで、切り替えがスムーズになります。
J/P(判断・知覚)で見るスケジュールの組み方
J/P(Judging/Perceiving)は、MBTIで「物事の進め方やスケジュール管理の傾向」を示す指標です。
- J(Judging/判断)
- 計画を立てて順序通りに進めるのが得意なタイプ
- P(Perceiving/知覚)
- 柔軟に対応し、その場の流れで進めるのが得意なタイプ
計画通りに動く安心感を求めるか、その場の柔軟さを優先するかで、対策の方向性も変わります。
J(計画型)
スケジュール通りに進むことに安心感がありますが、予期せぬ変更や遅延がストレスになりやすいです。
最初から予備日をスケジュールに組み込んで、計画に“余白”を持たせることで、変更にも柔軟に対応できます。
P(柔軟型)
柔軟型人は、その場の判断や臨機応変な対応が得意です。ただし、締切直前まで着手が遅れる傾向があり、突発的な予定に弱くなりがち。
対策のポイントは、実際の締切よりも早い“前倒し締切”を設定し、それを誰かと共有しておくこと。他者の存在が適度なプレッシャーとなり、着手の遅れを防ぎやすくなります。
MBTIは“ADHD診断”ではなく、自分を動かすヒント


「ADHDに多いMBTIタイプ」という情報は、あくまでネット上での憶測や体験談にすぎません。重要なのは、このような情報を“自分ごと”にどう変えるかです。
MBTIは診断ではなく、自分の脳の使い方や行動のクセを整理するための地図のようなもの。



そして地図があっても、進む道をつくるのは自分!
「このタイプだから自分はこう」と決めつけるのではなく、そのMBTIの特徴をヒントに環境や習慣を試行錯誤していくことが大切です。